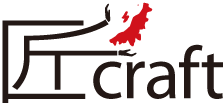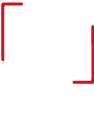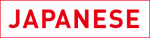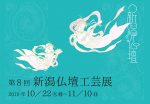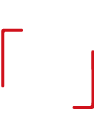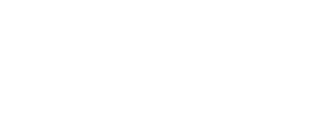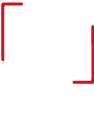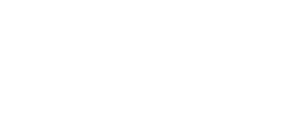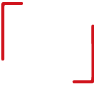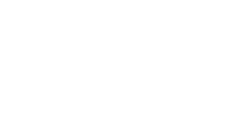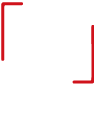たくさんのご来場誠にありがとうございました。

The 14th Niigata Butsudan(Buddhist Altar)Exhibition
伝統的工芸品 新潟仏壇 「未来へ繋ぐ伝統の技」
現代仏壇と新作小物の展示&ワークショップ&伝統工芸士の実演
毎年恒例、秋の「新潟仏壇工芸展」が10月より開催されます。今年も会場は旧小澤家住宅にて、熟練仏壇職人の皆さんによる展示、毎年人気の製作体験、実演を行います。
好評連続企画 いけばなと漆のコラボ展示
漆で魅せる”今”のいけばな「花×漆 -新潟はなうるし」
一昨年に始まり好評の連続企画、いけばなと漆のコラボ展示が今年も藤の間を中心に展開されます。いけばなの一部展示には、新潟仏壇組合の職人たちが製作した漆塗り花台が使用され、お花と漆技術の饗宴をご覧いただけます。他にも厳かな礼式生の実演や、いけばな体験(要事前申し込み)が開催されます。
2025年 10/11㊏〜11/3㊊㊗

OPEN 9:30ー17:00(10/14火・20月・27月は休館)
※観覧券の販売は16:30終了
会場:北前船の時代館 旧小澤家住宅(新潟市文化財)
新潟市中央区上大川前通12-2733 tel. 025-222-0300
Google map
観覧料 一般:260円 小学生・中学生:130円
※10/18・11/1は和服での来館者は観覧料無料
※11/3 文化の日は観覧料無料
※土日祝日は小中学生無料
主催 新潟仏壇組合・旧小澤家住宅 共催 新潟市
※展示内容や実施日は変更になることがあります。最新の情報は新潟市のサイトでご確認ください。
仏壇の技を生かした小物の展示

展示会ではお仏壇だけでなく、仏壇製作の高度な技術を生かした小物もバリエーション豊かに並びます。各工房それぞれの技とアイディアが光った逸品や、新潟県加茂市の伝統的工芸品「加茂桐簞笥」とのコラボ作品など、多くの作品の中からきっとお気に入りが見つかることでしょう。
新潟仏壇 挑戦の歩み

蔵の展示では、新潟仏壇組合のメンバーが力をあわせて挑んできた、これまでの取り組みをご紹介します。特に平成13年から18年にかけて、産官学の取組で試作製作された現代仏壇のバリエーションにご注目ください。その他、新潟市で開催された水と土の芸術祭における、アートワーク制作への協力事例などもパネルでご覧いただけます。
ワークショップ
10/19、26、11/3は、仏壇の匠たちによるワークショップ を行います。金具、蒔絵の技術を使った製作体験は、小学生以上からどなたでもお楽しみいただけます。(事前申し込み不要)
体験時間は約30分。製作物はお持ち帰りできます。 費用:金具、蒔絵共に1,000円
金具打ちによるネームプレート作り
10/19㊐・26㊐ 午前10:00〜12:00/午後13:00〜16:00

蒔絵によるネームプレート作り
11/3㊊㊗ 午前10:00〜12:00/午後13:00〜16:00

伝統工芸士による実演
11/2㊐・3㊊㊗ 伝統工芸士による蒔絵実演
台所奥の土間で、蒔絵師による製作実演をご覧いただけます。精緻で華麗な蒔絵技術をぜひ間近で堪能してください。

漆で魅せる“今”のいけばな 花×漆 –新潟はなうるし
日本の伝統家屋にあわせ美しさを追求し発展してきた「いけばな」と「うるし」。
明治期の新潟町の暮らしと文化を伝える旧小澤家住宅でいけばなを展示します。
いけばな協力 須田寛子社中(池坊)
※新潟仏壇組合員製作の漆塗り花台を、いけばなの一部展示に使用しています。


いけばな体験
11/1㊏ 15:00〜 いけばな体験を行います。
畳の間に座して姿勢を直し、お花をいけるワークショップです。(所要時間:60分、定員10名)花材のみお持ち帰りいただけます。和室での実施につき靴下着用でお願いいたします。
会場:松の間 参加費:3,000 円(税込)観覧料別 当日入館時に受付でお支払いください(現金払いのみ)
要事前申し込み:旧小澤家住宅 TEL 025-222-0300 または 会場の問い合わせフォーム より
参加希望日時と共にお申し込みください。申込期限:10/26(日)まで

いけばな「礼式生」実演
10/18㊏・11/1㊏ 13:30 〜 いけばな「礼式生」実演 を行います。
会場: 松の間 無料・申込不要・観覧料別
「礼式生(れいしきいけ)」は、花をいける所作をお客様の前で行う作法で、その起源は室町時代にさかのぼります。今回は旧小澤家住宅所蔵のお道具と、新潟仏壇組合製作のお道具を用いて、私たちのいけばなの心を表現したいと思います。
※ 10/18・11/1は和服(着物)での来館者は観覧料無料です。


展示会フライヤー(PDF)ダウンロード
新潟仏壇 五職の匠について
仏壇は、5つの専門工程による分業で製作されます。
木地師
良質の天然木を用い、ほとんど釘を使わない組み立て方式。仏壇の土台となる原型を細部まで造ります。
彫師
平彫り、丸彫り、立体感を出す重ね彫り等、何種類もの彫刻刀を駆使して仏壇内部の図柄を彫り出します。
金具師
銅や真鍮にタガネで丹念に打ち出します。飾り金具の多さと魚々子(ななこ)紋様が新潟仏壇の特徴です。
塗師
下地を塗り、何度も繰り返し漆を塗り仕上げた後、金箔を一枚ずつ貼っていきます。その後、組み立ても行います。
蒔絵師
漆を使い様々な絵模様を描き、金粉等で着色します。美しい蒔絵を多く使用しているのも新潟仏壇の特徴です。
新潟仏壇組合とは
新潟の街で仏壇業を営む同業者の集まりが起源で、最古の店(昭和中期に閉店)は元禄年間創業と言われています。
その後、明治・大正の殷盛期を迎え大正6年に新潟市佛壇業組合を設立、昭和24年に発足の新潟県宗教用具協同組合を経て、同52年に新潟市仏壇業協同組合を設立(当時43事業所)。同55年には伝統的工芸品産地の指定を受けました。
現在は5事業所(内、伝統工芸士7名)で、伝統的技術・技法の伝承、その他の信仰事業の推進活動を続けています。
新潟仏壇組合 事務局 e-mail:haga-fba@ec2.technowave.ne.jp
皆様のご来場、心よりお待ちしています。